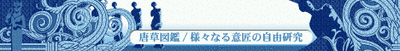シンボリズム
錬金術の3つのシンボル 太陽
 本来の「錬金術」は、金儲けを目的とするものでなく、全てのものの元型(原理)を求める、哲学や宗教や科学の知恵と共通するものである、と。大槻真一郎編著
『記号図説 錬金術事典』(同学社 1996)の序に。
本来の「錬金術」は、金儲けを目的とするものでなく、全てのものの元型(原理)を求める、哲学や宗教や科学の知恵と共通するものである、と。大槻真一郎編著
『記号図説 錬金術事典』(同学社 1996)の序に。
 このページは、2006年のもので、「錬金術の3つのシンボル」
は、「太陽」(金)の他に、たぶん「月」(銀)等を見たと思うのだが、ページが見当たりませんwww
このページは、2006年のもので、「錬金術の3つのシンボル」
は、「太陽」(金)の他に、たぶん「月」(銀)等を見たと思うのだが、ページが見当たりませんwww
(pro.tok2.comというサイトに置いていたものです)
その後、ローマの国立博物館やルーブルでヘルマフロディトス を見たので、とりあえず再アップします。残りのページもまた・・
| 陰陽 |
両性具有
一般に,男女両性を兼ねそなえた存在のことをいい,ギリシア語ではアンドロギュノスandrogynos。これに関して最もよく知られる物語は, プラトンの《痢宴 (シュンポシオン) 》に登場するアリストファネスの演説であろう。昔,人間には男と女のほかに,両性の結合した〈男女 (おめ) 〉と呼ばれるものがあり, 3 者とも手足が 4 本ずつ,顔が二つ,隠し所が二つあった。だが,ゼウスがこれらを両断したため,二つに分かれた本性は互いに己が半身にあこがれて結合しようと求め合う。したがって〈男女〉の半身のうち,男は女を,女は男を求めることとなる。男女間の愛を,原初の完全存在に対する憧憬として説明するのに,この物語がしばしば引合いに出されるゆえんである。
しかし,アンドロギュノスとしての原初的存在は,さらに古く世界各民族の宇宙創成神話に痕跡をとどめている。宇宙開闢 (かいびやく) 時には,世界は性的に未分化の〈卵〉であり,その潜勢的な産出力により神々と万物が分かれ出た。かくて始原にあるのは両性具有者なのである。この神話においては,世界創造は存在の分化・発展であると同時に,根源からの離反・堕落でもある。性の区分も例外ではない。それゆえ人間は,時を選んで神話を反覆・再演する宗教儀礼を通じて,未分化の原初的統一体へと回帰しなければならない。例えば婚礼や成年式において男女間で行われる衣装交換は,象徴的に両性具有者となることによって,個別の性を始原の存在に再統合するイニシエーション的儀式なのである。
哲学の分野では,両性具有のテーマは〈反対の一致〉〈全体性の神秘〉として登場する。 J.S.エリウゲナの《自然区分論》では,実体の区分は神において始まり,漸次人間の本性にまで下降して男女の区別が生じる。ゆえに実体の再統合は,逆に人間から始めて,神を含む存在の全体へと統行しなければならない。かくて神→自然→神という円環が完成される。これが世界の終末であり,最終段階で男女は再統合され,両性を超越した存在となる。復活のキリストはその先駆けであった。両性具有をシンボルとする玄義は,グノーシス主義や錬金術にも濃厚である。特に錬金術のシンボリズムは一種の汎性論ともいうべく,太陽,火,硫黄を男性,月,水,水銀を女性とし,錬金作業を両性の婚姻としてとらえた。したがって作業の原材料 (第一原質) も,窮極物質たる〈賢者の石〉も,ともに両性具有神の図像で表されることが多い。アニマ‐アニムスなる対概念で,男性の内に潜む女性,女性の内に潜む男性を想定したC.G.ユングが,精神分析学の観点から錬金術研究に赴いた際にも,この性的シンボリズムが一つの手がかりとなった。
両性具有の神話は,文学においてはドイツ・ロマン派に開花したほか,スウェーデンボリの影響が濃いバルザックの小説《セラフィータ》で最も魅惑的な表現を得た。なお,このシンボリズムでは,ヘルマフロディトスも,両性具有神としてアンドロギュノスと同義に用いられる。
平凡社大百科事典 有田 忠郎
ヘルマフロディトス Hermaphroditos
ギリシア神話の男女両性をそなえた神。ヘルメス Herm^s とアフロディテ Aphrodit^の合成語。オウィディウスの《転身物語》によれば,ヘルメスとアフロディテの息子で,泉のニンフ, サルマキスSalmakisに恋され,彼女と一体となったため,男女両性をそなえることになった,と説かれる。
美術作品としては,すでに前 4 世紀中ごろから立像のヘルマフロディトスが作られ (パリ,ビブリオテーク・ナシヨナル),最古のタイプと考えられている。造形上は,若いディオニュソスもしくはアポロンの姿を基本とし (ディオニュソスの従者としても表される),乳房のある少年,男根をそなえた女性として表現された。牧歌的主題を志向するヘレニズム文化においてヘルマフロディトスはかっこうの対象となり,文学・美術にしばしば取り上げられた。ヘレニズム後期には《まどろむヘルマフロディトス》 (ルーブル美術館,ローマ国立美術館) など,美少年アッティス Attis の図像を借用し,裸体伏臥の姿で表されることが多く,帝政期ローマにも継承された。近世では,スプランヘル,F.アルバーニなどに作例がある。
平凡社大百科事典 青柳 正規

Antonio Maria Zanetti -
Study of a relief decorated with a Hermaphrodite;
in the Palazzo Colonna
両性具有

錬金術のシンボルとしての両性具有。
M・マイアー 『黄金の卓の象徴』(1617)
Michael Maier, 1568 - 1608(1622)(en.wikipedia)
古代においては、男性的なものと女性的なものを双方をそのうちに秘めた人物としてイメージされている。
原初の存在としての両性を兼ね備えた生物が登場し、どこから互いに補完史うような2つの存在が生まれ出ている。
必ずしも性的な意味を持つとは限らず、「二元性と完全性」というテーマと深いかかわりを持つ。(✳二元原理)
(『世界シンボル事典』p479 上の図も)
二元原理 duality
互いの緊張関係がシンボルとしてのみを生むような、対立する2つの要素の組み合わせ、それぞれの要素が単独で用いられる場合よりも、活力を帯びた表現になっていることが多い。
あらゆる対概念は、こうした関係を生み出す両極となる可能性を秘めているがk「代表的なものとしては、
昼/夜、男/女、生/死、動物/人間、陰/陽、天/地、神/悪魔、上/下,無垢/罪、太陽/月,硫黄/水銀(燃焼性/揮発性)
新た二元原理を導入して世界を秩序付けようとする絶えざる営みは、人類にとって、明らかに「元型(アーキタイプ)」的性格をもつものと思われる。 (『世界シンボル事典』p301)
錬金術記号(wikipedia)
| INDEX | アカンサス | ツタ | ロータス | ブドウ | ボタン | ナツメヤシ |